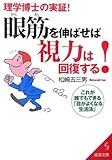▼健康日本21地方計画
- 事例集
- 新潟大学大学院医歯学の教授である安保徹氏は、近年多発する、子宮筋腫になる女性の共通点として、原因の中のひとつに、忙しすぎる、そして「夜更かし」する女性が多いと指摘しています。やはり規則正しい睡眠は健康を保つ上において重要なようです。
- 8月24日には人気歌手の大黒摩季さん(40)が重度の子宮腺筋症、左卵巣のう腫、子宮内膜症、子宮筋腫と子宮疾患4つも併発しているため、10月末から無期限で活動を休止すると発表されました。その上、流産も繰り返していたようです。
- 子宮系も含めガンや脳に対する病気が急増する背景には、水道水に含まれる大量の塩素系化学物質。あらゆる病気の原因を作り出す肉食と牛乳などの動物性タンパク質の過多。白砂糖、化学塩、食添加物、農薬だらけの安易なインスタント食品や加工品、ファーストフード、コンビニで販売しているジュース類などに偏った食生活。
- 身の回りに溢れる携帯電話などの電磁波。化粧品やシャンプー、ボディソープなどに強烈に含まれる有害物質。そしてアンバランスな睡眠。女性に増えた喫煙や受動喫煙…
- 毎日口に入れる食の安全には無関心で何でも食べてしまい、毎日肌に塗りつける有害性の高い日用品にも無関心、恐ろしい電磁波被害については考えもしない、そして不定期な睡眠や夜更かしをしていたら…病気は当然の結果となります。結果とは自分が作り出す行動に他ならない。
- 肉食は控え、動物性タンパク質は減らし、コンビニ食、ファーストフードは避けて、自分達が食す分ぐらいはせめて自炊する。水道水や電磁波に意識を持てば、いくらでも対策方法はあります。化粧品や日用品も意識すれば安全なものは沢山あります。タバコなどは絶対に止める!
- 病は、忘れることによって治る。
- 自分を生き生きとさせているものは何か、自分がしたいことは何かを自問する。あなたの人生で、みずからの情熱を表現する方法を見つけよう。
- ストレスや痛みや傷も含めて、あなたの体が経験してきたことを、絵に描くか、雑誌などから写真を切り貼りしたコラージュで表現してみよう。
- 次に、この先あなたの体に経験させたいことを絵かコラージュで表す。きれいに作ろう。
- それから、1枚目から2枚目に移るために必要なステップも自分の目的を思い出し、喜びと満足を求める旅の精神的支援にしよう。
- 若い人と接する時間を持とう。子どもを抱きしめたり、本を読んであげたり、一緒に遊んだりしよう。彼らの与えてくれる驚きは、あなたの滋養になる。
- 高齢者と接する時間を持とう。彼らと親しくなり、彼らから学ぼう。彼らの人生の話を聞かせてもらうために家に招く。
- あなたを知恵の世界に導いてくれる年長の指導者を見つけよう。
- あなたに生きることの意味や重要性を教えてくれた人物や出来事の話を、家族や友人にしてみる。
- 友人を招いて一緒に星を見る。あるいは、日の出や日の入りを見る。
- 必要なときは助けを求めよう。
- あなたの人生で記念すべき日に、友人や愛する人を招待しよう。あなたが旅してきた人生の話をしよう。
- 誕生日には毎年、それまでにやらなかったことをしてみる。
- あなたの信じる大義のために時間や金を費やそう。よりよい世界のために活動している組織や人々を支援しよう。
- 人間の最高の可能性のために戦おう。
■食生活について
- なるべく、頭の先から足の先までを一緒に食べられるものを食べる。豆とフルーツと小魚、卵、納豆、もやし、海藻、もずく、豆腐
- 毎食1合のご飯は多い。半合に減らそう。
- 1日の食事も量と回数を減らしてみる
- お酒も無理して飲まない。週に2回を超えたら調整する。
- メインディッシュを食べすぎないようにするには、メインディッシュを最後にすればいいのでは。「野菜やフルーツを食べられる人の場合は、食事の最初にとるといいそうです。簡単な上に、そのあとのメインを食べ過ぎなくて済みます。例えば「ステーキを食べる前に必ずサラダやフルーツスムージーをとるようにする」、それだけのこと。」
- たとえ何年もの間ひどい食事をしてきたとしても、健康的な食事を始めれば、驚くほどの違いが出るはずだ。その理由のひとつは次のことにある。人間の体は死ぬまで変わらない構造物だと思っている人もいるかもしれないが、実は組織のほとんどは常に新しくなっているのだ。例えば、胃の細胞は5日で入れ替わり、赤血球は4ヶ月で入れ替わる。成人の肝臓の細胞は300日から500日で全て新しくなる。骨でさえも最初のものがずっと続くわけではなく、人間の骨格全体は約10年で入れ替わるのである。体の細胞の大部分が常に再生されているのだから、今日あなたが食べるものが、明日のあなたの体を作ることになるのだ。
- 自分のとる食物に注意すること。それは自然で健康にいいものか、あなたの体と心の健康と調和しているかを問いかけてみよう。
- 台所に行って、あなたが健康に暮らすためにならない食べ物を捨てよう。
- 自分の体を汚染してはならない。ジャンクフードを食べてはいけない。
- 栄養価の高い食品を食べているのならば、カロリーを計算しる必要はない。
- 食べ物はゆっくり食べて、充分に噛んで、消化をよくする。腹一杯になる前でやめておく。あなたの体が食べた量を把握するのには20分かかるので、
- 時間をかけて食べるようにしよう。
- 可能ならば、地元の農家が営む店や地域コミュニティが支援する農業に参加して、生産者から直接に農産物を買うことにしよう。そうでなければ、自然食品を売る店を利用する。ラベルをしっかりと読んで、栄養価の高い原料を使った食品を選ぶようにしよう。
- まとめ買いをして、金と包装を節約しよう。
- 部分水素添加油を含む食品を買ったり、食べたりしない。食品が腐ったときの悪臭を覚えておいて、木の実や種や穀物製品にいやなにおいがしたら、食べてはならない。
- 糖分の多いコーンシロップは避ける。ケチャップは果汁で甘みをつけている無農薬ブランドのものに代える。ジャムは砂糖を使っていない果実100%のものを探そう。
- マヨネーズは、より体にいい大豆油かキャノーラ油を使ったものにする。豆腐やテンペ(発酵大豆を掲げたインドネシア料理)などの100%大豆食品を食べよう。
- 肉はあまり食べないか、まったく食べない。タンパク質は大豆やそら豆、えんどう豆、全粒穀類や木の実(ナッツ)から得る。
- 肉を食べるのならば、放し飼いにしていて、有機肥料で育てた家畜の肉を買い求めよう。魚を食べるのならば、養殖ではなく天然もので、水銀の含有レベルが低いものにする。果物と野菜は、できるかぎり缶詰ではなく新鮮なものをたくさん食べよう。
- 新鮮なものが手に入らないときは、缶詰よりは、塩や砂糖を加えていない冷凍ものがいい。
- ポテトフライやレタス以外にも、驚くほど多くの野菜があることを知ろう。種類の多い新鮮な野菜を楽しく味わおう。特に、ケールやコラード、カラシ菜、ホウレン草、トウチシャ、ブロッコリーなどの濃い緑の葉の野菜を多く食べる。
- できる限り地元で取れる旬の食べ物を食べよう。
- 小麦粉を使ったパンやクラッカー、菓子などはあまり食べない。全粒穀物、豆類、サツマイモ、野菜を多く取る。
- チョコレートを食べるか、コーヒーを飲むのであれば、適正な価格で有機製法のものを選ぼう。濃い色のチョコレートの方がカカオの割合が高いので、健康によい。
- 有機栽培の食品を買って食べる。可能ならば、みずから有機野菜を育ててみる。ケールやコラードを夏の終わりに植えれば、冬中、新鮮な青物が食べられるだろう。
- 遺伝子操作をしている食品に表示をするよう要求していこう。
- 昼食は弁当を作ろう。人の弁当を作るときには、愛情を込めたメモを添えてみる。
- 子どものためにパンは自分で焼く。健康的な食事を作る作業に子どもを関わらせよう。ブルーベリーやバナナなど子どもの好きな果物を使った全粒マフィンを作ろう。
- 子ども達が夕食を待っているときに、緑の葉のサラダを出してみよう。腹ペコのときの子どもはなんでも食べるはずだ。サラダにはレタスの他は、ニンジンや他の野菜も刻んで入れよう。
- デザートや簡単に調理できるパッケージ食品は健康によいものを選ぼう。
- スナックにする種や木の実、ホムスを塗った野菜は、冷蔵庫の目につきやすく、とりやすいところに入れておく。
- 食品の自然の色は目を楽しませるだけでなく、抗酸化物質など重要栄養素のしるしでもあることを知り、様々な色合いの食品を食べよう。
- 噛むとバリバリと音がするものを食べたいときは、塩を大量に含んだポテトチップスではなく、生野菜や木の実を食べる。
- 数日毎に、無農薬で作られた亜麻の種を電気コーヒーミルで挽いて冷蔵庫に保存しておき、毎日の食事に振りかけよう。シリアルやサラダ、サンドイッチやシチューによく合う。
- 毎日、新鮮な野菜を大量に食べよう。大きな鍋で野菜スープを作り、大きな容器に入れて冷蔵庫に保存し、少しずつ温めなおして食べればいい。
- 穀物は精製していない全粒のものを食べる。フライドポテトではなく、皮ごと焼いたジャガイモを食べる。野菜スープはスーパーにある塩分の多いものではなく家で作ろう。「有機」や「減塩」、「塩分控えめ」と表示された食品を求めよう。
- 食事と食事の間にはきれいな水をたくさん飲む。ソフトドリンクやダイエット炭酸飲料は飲まない。ハーブティーはおいしいだけでなく、健康にもよく、特に寒い日に最適だ。
- 料理油には、オリーブオイルやキャノーラ油のような単価不飽和油を使う。油は煙が出るまで熱さない。脂肪分は、アボガドやクルミ、アーモンド、ハシバミの実、ヒマワリの種などの種や木の実でとる。
- 酪農製品や脂肪の多い肉を避け、飽和脂肪をとらないようにする。
- オメガ6不飽和脂肪を多く含んだ油の使用は最小限に抑える。つまり、コーンやベニバナ、ヒマワリ、大豆、綿実の油である。
- 不飽和脂肪はとらない。マーガリンや市販の菓子、油で揚げた食品、出来合いのスナックやインスタント食品は避け、野菜不足にならないようにする。
- 外食するよりも友人を自宅の夕食に呼ぼう。自分も友人の家に招かれて、そのときには、おいしく健康的な食事を持参しよう。
- 健康的な食品を提供するか、少なくともあなたの要望に応じてくれるレストランだけをひいきにしよう。
- 異なる食習慣を持つ人と交流するときに、自分がすばらしい健康に向かって歩んでいることを恥ずかしいと思う必要はない。あなたの情熱と生命を大切にする気持ちを彼らにも伝えてあげよう。
- 健康な体で、みんなと仲良く生きるには自分たちで自ら土を耕し、良い種子と良い肥料と勤勉な世話で実りを上げた食べ物を採ること。
- 満腹の状態では、生きたいとは思わない。飢えていると、生きたいと切に思う。お腹が空いてたまらないと、食べたいと思うわけです。食べたいというのは生きたいというのに繋がります。その意味で昔の子どもたちは、お腹が空いていたから生きたいと切に願っていた。子どもたちは生きたいと、きらきら目を輝かし、耳を研ぎ澄まし、そして香りや風や、いろんなものを体いっぱいに受けて生き生きと餓鬼だった。その中の大将というのは、やっぱりすごかったな、と思うのです。
- 食事を腹八分におさえる。「ま、腹八分はささいなことに見えるかも分からんけど、これ、今日からずっとやってみ。食べたいと思ても腹八分で必ずおさえるんや。そうやって自分で自分をコントロールすることが楽しめるようになったら、生活変わってくるで」
■飲み物について
- 牛乳は重要な栄養素をバランスよく含み、必須アミノ酸の組成も理想的。カルシウムの含有量は、全食品のトップクラス。
- 牛乳より豆乳を飲むのがよい。
- 子どもにはソフトドリンクではなく、果汁ジュースを飲ませる。
- コーヒー
- コーヒーは頭痛、胃痛をなだめ、眠気をはらう煎じ薬として世界に広まった飲み物。
- 1日に5杯以上コーヒーを飲む人の肝臓がんの発症率は、飲まない人の4分の1。コーヒーの抗酸化・抗炎症成分がC型肝炎の進行を抑え、肝臓がんへの進行をくい止めるのではないかと推測されている。
- コーヒーを飲まない人を1とすると、毎日1杯以上飲む人は男性で0.81。女性は0.43と、女性では大腸がん発症率が半分以下に抑えられた。
- コーヒーを1日2杯以上飲む人は、飲まない人に比べて死亡するリスクが10%以上低い。
- コーヒーを1日6,7杯以上飲む人は、2型糖尿病の発生率が0.65倍。
- タバコを吸わない女性の場合、コーヒーをよく飲む人ほど脳卒中のリスクが下がる。
- 1日2-3杯のコーヒーを飲む男性は飲まない男性に比べて、胆石になるリスクが40%低い。
- コーヒーを飲む量が多い人ほど、シミの量が少ない。
- 日本酒
- 日本酒でガン予防。血液中にあり、ガン細胞を死滅させるNK(ナチュラルキラー)細胞を、日本酒に含まれる100種類を超える微量栄養素が活性化させます。
- 日本酒で動脈硬化を防ぐ。動脈硬化の原因は悪玉コレステロール自体ではなく"酸化変性した"悪玉コレステロール。これを抑制する抗酸化物が醸造酒(日本酒・ワイン)に含まれています。
- 日本酒はボケを防ぐ。記憶の保持や学習機能は、大脳にある"バソプレッシン"と呼ばれるホルモンの神経伝達によって行われ、何らかの理由で正常に働かなくなると痴呆の発症につながると考えられていますが、最近日本酒の中から3種類のタンパク質の酵素が発見され、これらが学習や記憶に有効な働きをすることがわかりました。
- 日本酒で骨粗しょう症を予防。この病気にはこれといった治療方法はないのですが、適度な飲酒が発症を遅らせ、症状を軽くさせることが分かってきました。
- 日本酒は蒸留酒より肝臓にやさしい。日本酒を飲んでいるとアルコール性の肝硬変になりにくい。実際に日本酒消費地域の東日本の方が焼酎消費地域の西日本に比べて肝硬変による死亡率が低い。これは日本酒の中に100種類以上の栄養素が含まれているからと考えられます。
- 休肝日は必要です。酒が強いからといっても肝臓が丈夫とは限りません。アルコール代謝にはビタミンB類がたくさん消費されますので、それらを多く含む大豆、落花生、レバー、魚卵、卵黄、豚肉などを使った料理を肴に自分のペースで飲みましょう。また、休肝日をもうけて肝臓をいたわりましょう。
- 水
- ミネラルを含んでいる水はよい水だといわれますが、ミネラルウォーターのミネラルが動脈硬化の原因になりうるということに関しては、あまり説明がなされていません。また、炭酸ガスの入ったミネラルウォーターの場合、炭酸ガスは非常に強い酸性をもつため、体にはよくありません。いずれにせよ、自然に流れている水ではなく、ビンにつめられている水は気をつける必要があります。水は流れたがっているのです。
■サプリ・栄養分について
- コラーゲンはタンパク質の一種、グルコサミンは糖の一種。だから、サプリでコラーゲンやグルコサミンを摂るということは、わずかなタンパク質や糖を摂るのと同じことになる。体内に吸収されたアミノ酸の一部はコラーゲンやグルコサミンに合成される。
- コラーゲンは肌だけに利用されるのではなく、全身のあらゆる組織に存在して体や皮膚や臓器の形を支える構造材の役目を果たす。年をとると、そのコラーゲン合成能力が低下して、目に見える変化としては肌のハリが失われたり、保水性が落ちてシワができやすくなる。
- グルコサミンも全身の軟骨や結合組織のあちこちにあり、軟骨細胞を形作るために最も大切な栄養素のひとつ。そしてやはり、加齢と共に合成能力が落ちるし、軟骨のクッションはすり減ると増えないので、ひざの痛みなどが出てくる。
- 定期的に献血をすることで鉄分(老化の原因)を抑制できる。
- 塩
- 「塩分の摂取が最も少ないグループが一番長寿で、高血圧、心筋梗塞も少ない。」「世界の経済先進国でいちばん塩分摂取量の多い日本人は、世界最長寿である。」「ビタミンの欠乏は特定の病気を引き起こすだけだが、塩の欠乏は命を奪う。日本人の高血圧症の98%以上は、塩は関係ない。大多数の日本人にとって減塩は意味がなく、危険のほうが大きい。」
- 塩の成分、ナトリウムは脳からの命令を神経細胞に伝えるなど、命の維持に深く関わっている。血中ナトリウム濃度が下がり過ぎると、意識混濁、吐き気、血圧降下、失神などの深刻な症状を招き、最悪の場合は死に至ります。
■給食・社食・食生活について
- ある県の学校給食に出された大福があるが、3年以上経っても全然腐らないし、カビも生えない。大福などには大量の防腐剤と軟化剤が入っています。ハムでも腐らないのもあった。これらを全部、クルマに入れたまま3年間も、季節や時間によっては70度以上にもなる中に置いておいたが、腐っていない。ハムも学校給食に出た生ハムで、亜硝酸ナトリウムで着色され、防腐剤もはいっている。亜硝酸ナトリウムは発がん性が高い食品添加物と言われている。
- 国では、これくらいの量であれば食べても安心だ、安全だといって基準を出している。この種の食品を朝に食べて、さらに給食時に食べ、さらに夜に家でも食べるとしたらどうなるか。生活習慣病やがんに侵されたりする可能性が高い状態と言える。
- 凶悪事件を起こした中学生は、朝食はほとんど食べていなかった。昼食は、その中学校では給食がないため弁当で、おかずはハンバーグ、ソーセージ、コロッケなどの肉類。間食はスナック菓子やチョコレート、アイスクリーム、炭酸飲料などで、いずれも砂糖がたくさん含まれている。そして夕食のおかずは、約肉などの肉類。ほとんどいつも肉。カップ麺もよく食べており、毎日のスナック菓子もかなりの量に上っていた。「若者の暴力の増加の背景には、家庭問題、ドラッグ、貧窮などといった要因もあるが、おそらく最も重要な問題は、食である。」
- コロナでは社員の健康はもちろん、社員が安心して働けるために、その恩恵を家族にも広げたいと考えている。2011年から、安心安全な米や野菜を各々の社員の家庭にも供給する体制を作り始めた。社員とその家族の心と体の健康を、真剣に考えていると言える。会社というのは、単に社員を叱咤激励するだけでなく、社員が自発的に仕事に取り組み、創造性を発揮できるような仕組みにしなければ、経営効果が上がらない。現在のコロナは、社員の1人ひとりが、いかにして健康で最大限に能力を発揮できるかを考えている。
- 現代の子供の好き嫌いの激しさは、ごくわずかな幅の味の体験しかないことに端を発している。すでに「りんごの香りを嗅いでシャンプーを、ミントの香りで歯磨きチューブを連想するような子」が増えている。
■ファーストフードについて
- このような病気に悩む、また今後かかる女性は急増すると思われます。子宮系も含めガンや脳に対する病気が急増する背景には、水道水に含まれる大量の塩素系化学物質。あらゆる病気の原因を作り出す肉食と牛乳などの動物性タンパク質の過多。白砂糖、化学塩、食添加物、農薬だらけの安易なインスタント食品や加工品、ファーストフード、コンビニで販売しているジュース類などに偏った食生活。
- 肉食は控え、動物性タンパク質は減らし、コンビニ食、ファーストフード(ジャンクフード)は避けて、自分達が食す分ぐらいはせめて自炊する。水道水や電磁波に意識を持てば、いくらでも対策方法はあります。化粧品や日用品も意識すれば安全なものは沢山あります。
- タバコなどは絶対に止める!
- 「僕の考えでは、ファーストフードはアダルト・チルドレンを作るシステム。なにも、あの緊張病に陥ったような店員たちの幼稚な言語や、ディズニー的なインテリアだけを言ってるんじゃない。ああいう店には、プロの料理人はいらない。頭も使わずにすむから二重の意味で、プロの料理人の首を切るシステム。出されるのは、調理とは程遠い、世界中どこで食べてもいつ食べても同じ味。いいかい、食ってもんは、コミュニケーションの手段で、異文化との無言の対話。そして大人と食卓を共にすることは子供たちにとって社会化への糸口。食べ方も知らず、複雑な味覚の世界にも分け入らず、ファーストフード漬けの大人は、いわば閉ざされたエゴの殻にとどまっている子供のようなもの。食の世界的な均質化は、やがては食文化における父権の喪失をもたらすだろう。僕が懸念するのは、このままほっておけば、社会全体が、総大人こども化する羽目になるってこと。」
- 「問題は、あのひどい油で揚げたフライドポテトだ。数社のファーストフードチェーン店が、ポテトに塩と一緒に砂糖を加えている、幼児は甘味を好むから。指でもぐもぐとつまむ子供じみた様子もさることながら、あれは大人こども化以上に深刻な事態を招きかねない。高温で20分も揚げていれば油というものはどうしたって劣化して毒になる。植物油は熱に弱く、それも混合油が劣化したものとなれば、体にいいはずがない。肝臓には致命的。ものの本によれば、ゲルマン人の度重なる侵入にも関わらず存続し続けたほどの古代ローマが滅亡したのは、実はオリーブ油を保存しておく容器の内側に鉛を貼っていたせいで、この中毒で社会全体が衰弱していったのだという説がある。つまり、文化的衰退はフライ容器から始まる、という仮説が立てられる。」
- ファーストフードチェーンは、どこも質とサービスを売りにしている。けれど、質に関していえば、どこでもいつでも同じ味の安定した食べ物を供給するためには、どうしたって冷凍食品をじゃんじゃん使わざるをえない。テレビ・コマーシャルで強調するような新鮮な素材では先が読めず、危なっかしくて仕方ないからだ。もっと掘り下げれば、その商品は、あまり環境にも優しいとはいえない。フライドポテト用の大ぶりで長いじゃがいもを作るために、アメリカの北西海岸の環境に歪みが出ている。
- 食についてマスメディアで語られることといったら、工業生産でろくでもない食べ物を作っている当事者たちか、彼らに買われたジャーナリストやフードライターたちのコメントが大半。しかも彼らは、食というものの背景についてあまりにも無知。それでも第三世代は鵜呑みにしている。
- なぜ安いのかをよく考えてみること。牛も、鶏も、空間を最小限に節約した、ものすごい環境で育っている。労働力にしたって、たとえばメキシコのような国からの季節労働者を、保険もかけずにこき使う。手間をかけない、見かけ重視のステレオタイプな食品、形だけの中身がスカスカな食品。でも、消費者たちはなかなか目を覚まそうとしない。なぜって自分で時間をかけて作るよりもずっと早いし、それに安くつく、そう信じ込んでしまっているから。作れない人もどんどん増えている。
▼カップラーメンを激ウマに変身させるアレンジランキング
- ごま油 39.0%
- チーズ 16.3%
- 海苔 12.9%
- ネギ 9.6%
- たまご 9.0%
■海外から入ってくる食べ物について
- メキシコでは輸出用の野菜栽培のために農薬を多用している地域と、自家用の野菜栽培のため農薬を使っていない地域とでは、大きな違いがあった。違いとは、子供に「人の絵」を描かせると、その「人」が恐ろしいほど様子が異なったこと。4,5歳の子供も、6,7歳の子供も、農薬をあまり使っていない地域の子供は目も鼻も口も手も足も、ときには髪の毛も「人の絵」として、人間らしくきちんと描いている。ところが農薬多用地域の子供が描いた絵は、とても人の形にはなっていない。何を描いてあるか判別することも困難。
- 港にニワトリの餌が入ってくると知ると、検査担当の男の人たちは一様にいやーな顔をする。というのは、中身を調べるために、防毒マスクをしなければならないから。袋を開けたとたんに、中に充満していた農薬がバーっと吹き出る。もしも防毒マスクをしないで荷物を開けると、その農薬を吸って、その人は再起不能になってしまう。防毒マスクなしでは検査できない。そんな毒性の強いものを食べたニワトリが産む卵には、当然農薬が混入しているはず。